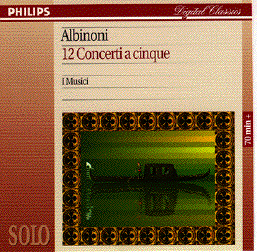 |
|
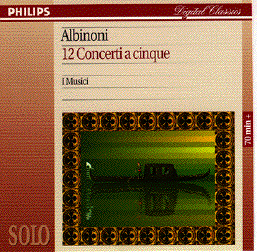 |
アルビノーニと聞いて、たいていの人は有名な「アダージョ」を連想すると思うが、彼は「アダージョ」だけしか曲を作らなかったわけではない。
あまり知られてない事であるが、彼はイタリア・バロック協奏曲の様式を同時代に生きたコレルリと同様に形成した先駆者であり、あのヴィヴァルディの先輩にあたる人物でもある。その作風は同国のみならず、ヨーロッパ中の作曲家に影響を及ぼし、バッハも自分の室内楽を作曲する時に、イタリア・バロック協奏曲の様式を随所に取り入れている。
このCDに収められている12の曲は、合奏協奏曲(コンチェルト・グロッソ)と呼ばれる形態のもので、古典派以降の交響曲の前身になった様式の曲である。曲は、3楽章で「急、緩、急」のイタリア・バロック音楽特有のリトルネロ形式をとっている。ヴァイオリン等、弦楽器が中心であり、通奏低音としてチェンバロが使われている。
全曲、明るくて快活であり、聞いていて疲れを覚えない。仕事をしながら聞くには打ってつけであろう。
ただ、このCDは、入手がかなり困難になると思われる。作者は、秋葉原の石丸電気で手に入れたのであるが、この時在庫はこれのみ1本であり、その後も足を運んだものの見かける事はなかった。
かなりのレアものであるが、ぜひ聞いてみていただきたい一品である。
フィリップス 1994年DDD録音 演奏:イ・ムジチ合奏団
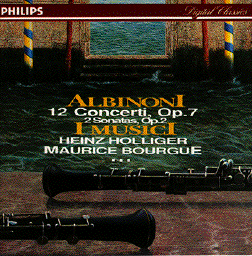 |
これもアルビノーニの協奏曲集であるが、今度は合奏協奏曲の形態ではなく、主役の楽器とそれを盛り上げる脇役の合奏集団との共演という協奏曲本来の形をとる。
この曲集の特徴として、弦楽器だけでなくオーボエと言う管楽器が加わり、12曲中8曲が、オーボエの協奏曲である。おまけとして、作品2のソナタが2つ入っている。
これも、作品5と同様のような感想をもつのであるが、全曲すべて長調の曲なので緊張感に欠けるため、ずっと聞いているとやや退屈してくるのが残念。
この曲集は、2枚組みであるため少々高価であるが、大きなレコード店では入手しやすい。秋葉原の大型レコード店では、確実に入手できるであろう。
オーボエの曲が好きな人にお勧め。
フィリップス 1992年DDD録音 オーボエ:ハインツ・ホリガー、モーリス・ブールグ 演奏:イ・ムジチ合奏団
 |
今度は、協奏曲集ではなく、トリオ・ソナタの曲集であるが、ゼレンカという作曲家を知っているという人は、相当のバロック音楽通であろう。
ゼレンカはチェコ出身でバッハと同年代の作曲家であり、バッハの死ぬ5年程前に亡くなった。
この時代の作曲様式に、出身地の民謡のリズムを取り入れた彼独特の作風は、多くの作曲家達を魅了し、バッハも彼の作曲技法には、一目置いていた程の人物である。
トリオ・ソナタは、協奏曲に比べて演奏者が4〜5人以下と言う小さな演奏形態をとり、楽章も3〜6楽章と様々であるが、一般的には4楽章の構成をとる。リズムとしては「緩、急、緩、急」の形をとり、リトルネロ形式に前置きが付いたと考えればよい。この曲では、オーボエ2つ、ファゴット、チェンバロ、コントラバスを基本とし、第3番の曲のみヴァイオリンが付く。演奏時間もこの時代のトリオ・ソナタとしては、1曲平均18分以上とずいぶん長めである。
曲の感想としては、オーボエとファゴットによる民謡的な曲の快活なリズムにコントラバスによる重みがついて、非常に面白くかつ、後味引かないスッキリした内容となっており、何か考え事をしていて思い詰まった時に、気分転換として聞くのに最適である。特にこの曲では、この時代としては珍しくコントラバスがうまく活躍できるように書かれているが、これは彼が当時の宮廷楽団で、コントラバスの演奏を担当していたためと思われる。
このCDの入手に関しては、作曲家がマイナーな人物であることも手伝って、はっきり言って99%不可能と考えられる。最新の録音の物では、大きなレコード店では可能であると思われるが、このCDの演奏メンバーによる演奏には到底及ばないであろう。それほどまでに、このメンバーによる録音は見事なものなのである。録音は、今から24年前と古く、マスターテープも長い間倉庫に眠っていたものを再びデジタルにリマスターしたのであろう、あまり音質はよろしくない。しかし、演奏については、最新の物と聞き比べて明らかにこちらの方が、作者としては素晴しく思われる。ちなみに、この演奏のCDを手に入れるために作者は、2年間月に5回ほど秋葉原の石丸電気のレコード店に通って偶然の発見を待ち続けた。
アルヒーフ 1972年ADD録音 オーボエ:ハインツ・ホリガー、モーリス・ブールグ
ファゴット:クラウス・トゥーネマン
コントラバス:ルチオ・ブッカレルラ
チェンバロ:クリスティアーヌ・ジャコテ
ヴァイオリン:スチコ・ガブリロフ
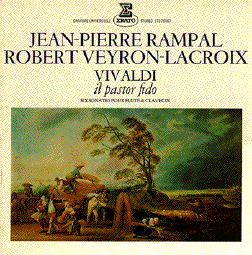 |
200〜300年の長い年月をへた古い時代の音楽作品では、しばしばその作曲者が誰かを確定することは、容易なことではない。現在、バッハやモーツァルトの様な、全て研究しつくされているように思われる著名な作曲家の場合でさえ、今だに未知の作品が発見されたり、一方では誰もが真作であることを疑わなかった作品が実は偽作であることが立証されて、作品表から抹消されるケースも珍しいことではないのである。
偽作や、作曲者が判然としない物については、その大部分が写本や出版業者のミスによるものであり、意図的に著名な作家の名を使って人を欺き、金を儲けようという、絵画の分野でよく行われる”贋作”はめったにない。しかし、この作品13のフルート・ソナタは、その珍しい事例の一つである。
この曲の作曲者であるニコラ・シェドヴィルは、フランスのオペラ座の奏者の他、宮廷オーボエ奏者、国王及び、貴族階級の息女のミュゼット教師を勤め、主にミュゼット(当時フランスで愛好されたバッグ・パイプの一種)の性能を発揮させるための曲を多く書いた人物である。彼が、当時名の知れた人物にもかかわらず、あえてヴィヴァルディの名を偽って出版したのは、ミュゼットのレパートリーの拡大を狙ってのことではなかったかと思われる。ヴィヴァルディの曲については、当時フランスの有名な音楽会”コンセール・スピリチュエル”で、あの「四季」の演奏が大好評を博したため、それ以降パリでは良く知られていたためである。それゆえに、ヴィヴァルディの素材を取り入れながら、イタリアとフランスの好みをうまく融合した作品をヴィヴァルディの名で発表すれば売れるのではないかと意図したのであろう。しかしこの曲集は、彼が期待した程の成功を得ることはなく、以後彼は再び自分の名で曲を発表するようになった。
曲の方は、作者が聞く限りにおいて、ヴィヴァルディが作曲したと言っても疑いようのない程の見事な出来映えである。この曲に当たっては、表題にどんな楽器で演奏してもよいと表記してあると解説書にはある。この事柄については、楽譜の売り上げを伸ばそうという、後期バロック時代の器楽曲でよく見られる営利目的以外のなにものでもないが、実際他の楽器での演奏(作者の場合オーボエの物を聞いた事がある)でも、素晴しいものであった。優れた曲は、演奏する楽器を問わないのである。この曲が当時売れなかったのは、公開演奏か何かで演奏した奏者がヘタだったためであろう。感想としてこの曲は、精神的に疲れた時あるいは、悩み事がある時に聞くとよい。フルートのやさしい響きと、ゆっくりした曲のリズムが心を潤してくれる。作者は、この曲を聞きながら、切羽詰まった浪人時代を乗り切った。
演奏は、ジャン・ピエール・ランパルのフルート演奏の物に限る。他の演奏者のものもFMで聞いたことがあるが、この人物の演奏の足元にも及ばなかった。録音は1968年と古く、音質もあまり良くないが、それを補うだけの素晴しい演奏であることは言うまでもない。発売元がエラートであるので、比較的手にいれ易く、値段も2千円未満であるので、CD店等で見かけたらぜひ入手してみてもらいたい。値段以上の価値は十分にある。
エラート 1968年ADD録音 フルート:ジャン・ピエール・ランパル
チェンバロ:ロベール・ヴェイロン・ラクロワ